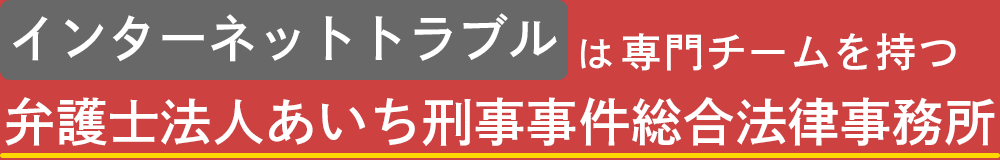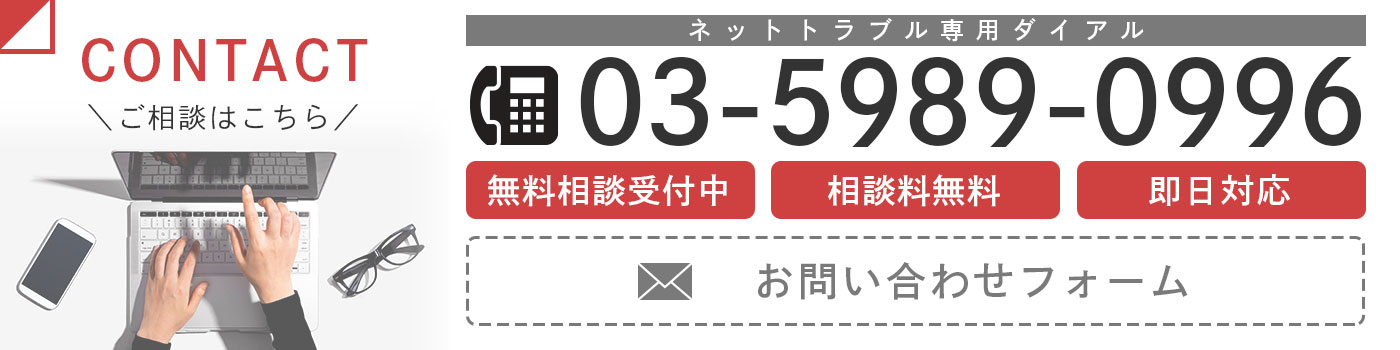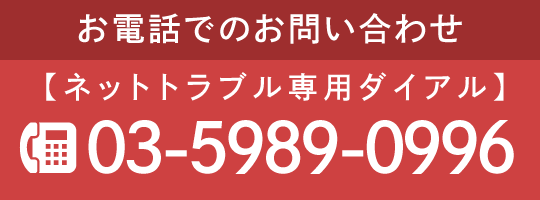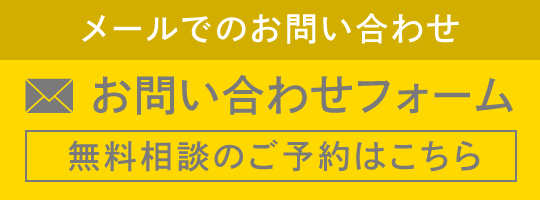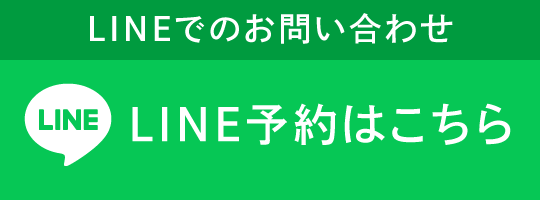インターネットを通して多くの情報のやり取りが行われるようになりました。しかし一方で、情報漏洩のリスクも大きくなりました。特に個人情報や秘密情報を漏洩してしまうと、重大な被害が生じかねません。
ここでは、インターネットでの情報漏洩について解説します。
インターネットで情報漏洩のリスク
情報漏洩のリスクとしては、電子メールの送信先の間違い、コンピューターウイルスによる被害などの場合があります。
また、SNSで職務上扱う情報を投稿してしまい、漏洩するおそれもあります。
公務員の守秘義務
国家公務員は、国家公務員法100条1項において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定められています。地方公務員についても、地方公務員法で同様に定められています(地方公務員法34条1項)。
この「秘密」とは、「非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるもの」とされています(昭和52年12月19日最高裁第二小法廷決定(徴税トラの巻事件))。
これらの規定に違反して秘密を洩らしたときは、いずれも1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。
特定秘密保護法
「特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)」では、「国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的」としています(同法第1条)。
特定秘密保護法では、「当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」が特定秘密として指定されます(同法3条1項)。別表には「一 防衛に関する事項」「二 外交に関する事項」「三 特定有害活動の防止に関する事項」「四 テロリズムの防止に関する事項」など、我が国や国民一般にとって需要な情報が含まれています。
特定秘密の取り扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を洩らしたときは、10年以下の拘禁刑に処され、情状によりさらに1000万円以下の罰金に処されます。特定秘密の取り扱いの業務に従事しなくなった後に漏らした場合も同様です(同法23条1項)。
また、行政機関の長が内閣に提示したり(同法4条5項)、外国の政府や国際機関に提供したり(9条)、国会両議院や裁判所など公益上必要の認められる相手に提供したり(10条)、内閣総理大臣が特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施のため特定秘密である情報を含む資料の提出を求めること(18条4項後段)により、特定秘密が第三者に提供されることがあります。これらの提供の目的である業務により当該特定秘密を知得したものがその特定秘密を洩らしたときは、5年以下の拘禁刑に処され、又は情状によりさらに500万円以下の罰金に処されます(同法23条2項)。
これらの罪は未遂も処罰します(同法23条3項)。また、過失により漏らした場合も処罰されます(23条1項の罪については2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。23条2項の罪ついては1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
公務員がこのような情報漏洩をすると、厳しい懲戒処分が下されます。
人事院の「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」によると、「1 一般服務関係 イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい」については、停職・減給・戒告処分の対象となります。「ア 故意の秘密漏えい」は免職又は停職となり、特に「自己の不正な利益を図る目的」の場合は、必ず免職となります。
個人情報保護法
公務員だけでなく、企業も個人情報という重要な情報を扱います。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としています(第1条)。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(第2条第1項第1号)や個人識別符号(第2条第2項)が含まれるもの(第2条第1項第2号)をいいます。
企業については「第四章 個人情報取扱事業者等の義務等」において定められています。
個人情報データベース等(同法第16条第1項・個人情報の保護に関する法律施行令(個人情報保護法施行令)第4条。個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものなど)を事業の用に関している企業などは個人情報取扱事業者とされます(同法第16条第2項)。
顧客の氏名などを検索すれば出せるようにすれば該当するので、顧客の氏名等の情報をデータとして保存している企業であれば、個人情報取扱事業者に該当するでしょう。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならず(同法第17条第1項)、あらかじめ本人の同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません(同法第18条第1項)。
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません(同法第19条)。
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません(同法第20条第1項)。
個人情報取扱事業者(法人の場合は、その役員)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部または一部を複製し、又は加工したものを含みます。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第179条)。法人の代表者や従業者等がその法人の業務に関しこの違反をしたときは、法人も1億円以下の罰金に処されます(同法第184条第1項第1号)。
まとめ
以上のように、インターネットで情報漏洩をすると、重大な事態になりかねません。
インターネットでの情報漏洩にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。