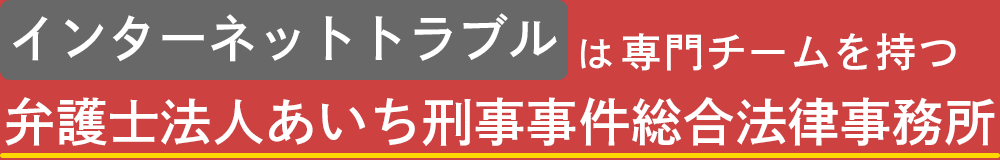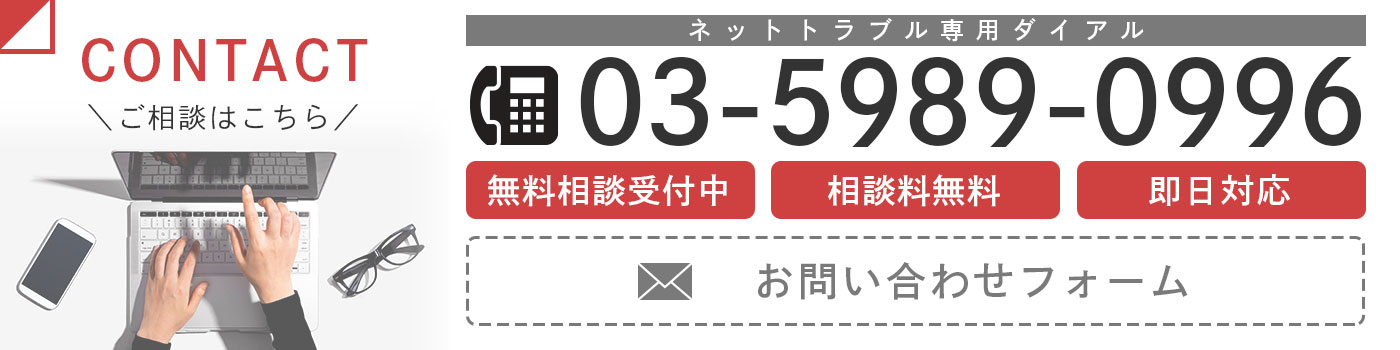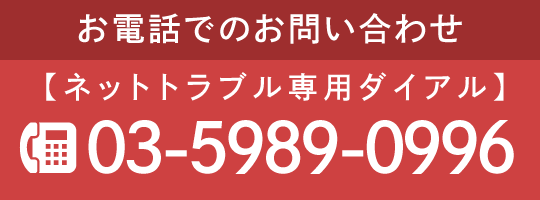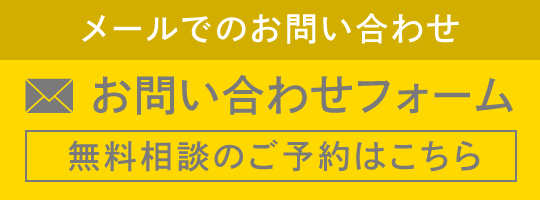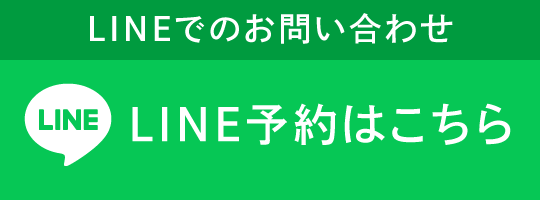Archive for the ‘ネットトラブル’ Category
インターネット上でのなりすましによる取り引き
インターネット上でのなりすましによる取り引き

インターネットでは、非対面でやり取りされるため、他人になりすまして取り引きが行われることがあります。
他人の名義を悪用した人を特定して責任を追及することは、現実には難しいです。
この場合、騙された側は損害を負ってしまうことがありますので、なりすまされた本人に対して責任追及ができるかが重要になってきます。
なりすましによる取り引きが行われた場合、なりすまされた本人は原則として責任を負いません。
本人とは全く関係なく取り引きが行われたのであれば、本人が責任を負わないのは当然です。
しかし一定の場合には本人が責任を負わされることがあります。
以下の民法の条文が関係してきます。
外観の存在、相手方の善意無過失、本人の帰責事由、があれば、下記条文を類推適用して、本人に効果が帰属し、責任を負わされることがあります。
(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
(権限外の行為の表見代理)
第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
(代理権消滅後の表見代理等)
第112条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
本人確認方法として、特定のIDやパスワード等が使用されているのであれば、他人により悪用された場合、原則として本人に効果が帰属されるように合意がなされている場合がほとんどです。
しかし、本人が消費者であれば、消費者契約法の以下の条文が問題となってきます。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(基本原則)
第1条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
事業者に帰責性がある場合、事業者からIDやパスワードが漏洩した場合、等は対象外になると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に12か所事務所がございます。
各事務所の所在地はこちらからご確認ください。
弊所への初回相談料は無料です。
無料法律相談のご予約は☎050-5830-9572までお電話いただくか✉https://nettrouble-bengoshi.com/inquiry/にてお問い合わせくださいませ。
暗号資産トラブル

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)に注目が集まっています。こうした新しい分野には、大きな経済効果を期待できる一方で、対面の取引はまず考えられず、過剰な広告、利用者を誤認させる詐欺的な取引、個人情報の漏洩、さらには暗号資産そのものの流出も問題になっています。
ここでは、暗号資産とそれに関わるネットトラブルについて解説します。
資金決済に関する法律
暗号資産について、「資金決済に関する法律」(資金決済法)では、次のように規定されています。
資金決済に関する法律
第2条
第14項
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
第15項
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
第16項
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
第17項
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
暗号資産によるトラブル
暗号資産は資金洗浄(マネーロンダリング)の手段としても利用されます。
特殊詐欺で送金させた詐取金を暗号資産に換えて送金するなどの手口が行われています。
このような悪用を防ぐため、暗号資産について、様々な規制が課せられています。
資金決済法では「第三章の三 暗号資産」(第63条の2以下)で規制されています。
暗号資産(仮想通貨)を扱うためには、暗号資産交換業者として登録する必要があります(資金決済法第63条の2第14項)。
この登録を受けないで暗号資産交換業を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第107条第12号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。
暗号資産交換業者として登録するためには、株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)であること(資金決済法第63条の5第1項第1号)、(資金決済法第63条の5第1項第3号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第9条第1項第1号)などの条件を満たす必要があり、条件を満たさないときは、登録を拒否されます(資金決済法第63条の5第1項柱書)。
登録後も、情報の安全管理(資金決済法第63条の8)、利用者の保護等に関する措置(同法第63条の10)、利用者財産の管理(同法第63条の11)などの規定を遵守し、利用者の保護を図らなければなりません。
暗号資産の性質について利用者を誤認させないよう、様々な規制が設けられています。暗号資産交換業の広告においては、暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないことのほか、暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を表示しなければなりません(資金決済法第63条の9の2)。この重要な事項として、①暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由、②暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること、が定められています(暗号資産交換業者に関する内閣府令第18条)。
暗号資産の売買契約の締結や勧誘などにおいて、虚偽の表示をしたり、暗号資産の性質について相手方を誤認させるようなことは禁止されています(資金決済法第63条の9の3第1号・暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条)。これに違反すると、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第109条第10号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も2億円以下の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第2号)。
資金決済法第63条の9の3第2号では「その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為」、第3号では「暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為」を禁止しています。これらに違反すると、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(資金決済法第112条第14号)。法人の代表者などが違反をした場合、法人も同額の罰金刑を科されます(資金決済法第115条第1項第4号)。
このように暗号資産は、新しい取引の可能性を持つだけでなく、様々なネットトラブルのリスクもはらんでいます。
暗号資産について不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
ネットにおける性犯罪

インターネット上で多数の性犯罪行為が行われております。
インターネット上の性犯罪は、簡単に行うことができてしまう特徴があります。
今回は、十六歳未満の者に対する面会要求等罪と、リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪について解説します。
<十六歳未満の者に対する面会要求等罪>
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。
上記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
実際に会ってわいせつ行為をしたら、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪等が成立します。
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3項)。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限り犯罪が成立します。
実際に送信させたら、不同意わいせつ罪が成立します。
<リベンジポルノ防止法違反・私事性的画像記録提供等罪>
リベンジポルノ防止法は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます。
この法律は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するとともに、私事性的画像記録に係る情報の流通によって名誉又は私生活の平穏の侵害があった場合における特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例及び当該提供等による被害者に対する支援体制の整備等について定めることにより、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としております(第1条)。
この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(第2条第1項)。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
画像は、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者である第三者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除きます。
「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、前記各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいいます(第2条第2項)。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(第3条第1項)。
前記の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同様に処されます(第2項)。
上記の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます(第3項)。
これらの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができません(第4項)。
まとめ
このように、インターネット上の性犯罪には様々なものがあります。
インターネット上で性的な画像を掲載されたり、提供を求められてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
ネットと情報漏洩

インターネットを通して多くの情報のやり取りが行われるようになりました。しかし一方で、情報漏洩のリスクも大きくなりました。特に個人情報や秘密情報を漏洩してしまうと、重大な被害が生じかねません。
ここでは、インターネットでの情報漏洩について解説します。
インターネットで情報漏洩のリスク
情報漏洩のリスクとしては、電子メールの送信先の間違い、コンピューターウイルスによる被害などの場合があります。
また、SNSで職務上扱う情報を投稿してしまい、漏洩するおそれもあります。
公務員の守秘義務
国家公務員は、国家公務員法100条1項において、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定められています。地方公務員についても、地方公務員法で同様に定められています(地方公務員法34条1項)。
この「秘密」とは、「非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるもの」とされています(昭和52年12月19日最高裁第二小法廷決定(徴税トラの巻事件))。
これらの規定に違反して秘密を洩らしたときは、いずれも1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(国家公務員法109条12号、地方公務員法60条2号)。
特定秘密保護法
「特定秘密の保護に関する法律(特定秘密保護法)」では、「国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的」としています(同法第1条)。
特定秘密保護法では、「当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」が特定秘密として指定されます(同法3条1項)。別表には「一 防衛に関する事項」「二 外交に関する事項」「三 特定有害活動の防止に関する事項」「四 テロリズムの防止に関する事項」など、我が国や国民一般にとって需要な情報が含まれています。
特定秘密の取り扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を洩らしたときは、10年以下の拘禁刑に処され、情状によりさらに1000万円以下の罰金に処されます。特定秘密の取り扱いの業務に従事しなくなった後に漏らした場合も同様です(同法23条1項)。
また、行政機関の長が内閣に提示したり(同法4条5項)、外国の政府や国際機関に提供したり(9条)、国会両議院や裁判所など公益上必要の認められる相手に提供したり(10条)、内閣総理大臣が特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施のため特定秘密である情報を含む資料の提出を求めること(18条4項後段)により、特定秘密が第三者に提供されることがあります。これらの提供の目的である業務により当該特定秘密を知得したものがその特定秘密を洩らしたときは、5年以下の拘禁刑に処され、又は情状によりさらに500万円以下の罰金に処されます(同法23条2項)。
これらの罪は未遂も処罰します(同法23条3項)。また、過失により漏らした場合も処罰されます(23条1項の罪については2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。23条2項の罪ついては1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
公務員がこのような情報漏洩をすると、厳しい懲戒処分が下されます。
人事院の「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)」によると、「1 一般服務関係 イ 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい」については、停職・減給・戒告処分の対象となります。「ア 故意の秘密漏えい」は免職又は停職となり、特に「自己の不正な利益を図る目的」の場合は、必ず免職となります。
個人情報保護法
公務員だけでなく、企業も個人情報という重要な情報を扱います。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としています(第1条)。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(第2条第1項第1号)や個人識別符号(第2条第2項)が含まれるもの(第2条第1項第2号)をいいます。
企業については「第四章 個人情報取扱事業者等の義務等」において定められています。
個人情報データベース等(同法第16条第1項・個人情報の保護に関する法律施行令(個人情報保護法施行令)第4条。個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものなど)を事業の用に関している企業などは個人情報取扱事業者とされます(同法第16条第2項)。
顧客の氏名などを検索すれば出せるようにすれば該当するので、顧客の氏名等の情報をデータとして保存している企業であれば、個人情報取扱事業者に該当するでしょう。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならず(同法第17条第1項)、あらかじめ本人の同意を得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません(同法第18条第1項)。
個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません(同法第19条)。
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません(同法第20条第1項)。
個人情報取扱事業者(法人の場合は、その役員)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部または一部を複製し、又は加工したものを含みます。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第179条)。法人の代表者や従業者等がその法人の業務に関しこの違反をしたときは、法人も1億円以下の罰金に処されます(同法第184条第1項第1号)。
まとめ
以上のように、インターネットで情報漏洩をすると、重大な事態になりかねません。
インターネットでの情報漏洩にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
盗撮画像を投稿された

盗撮された裸や下着姿の動画・写真が、インターネット上にアップロードされて、被害が拡大してしまうことがあります。
盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的姿態等は、以下の部分・姿態をいいます。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意わいせつ罪記載の以下に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪が成立し、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処します。
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立し、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
二 不同意わいせつ罪記載の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をし、又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
情を知って、不特定又は多数の者に対し、上記各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
情を知って、性的姿態等影像送信罪各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、性的姿態等影像記録罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処します。
このように、盗撮画像をネットに上げられても、犯人を処罰できます。
ネットに盗撮画像を挙げられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
国際的ネットトラブル

インターネットが発達し、世界中の様々な人たちと交流できるようになりました。一方で、対面では考えられなかったトラブルにも巻き込まれるケースが生じてきました。
ここでは、国際的なネットトラブルについて解説します。
オンラインの危険性
オンラインでは直接相手が見えませんし、声すらもないので、相手の年齢、性別、住所、国籍などが本当かもわかりません。
特に、SNSやオンラインゲームでは、親近感を抱いて、警戒が薄くなったところで、個人情報の提供を求められたり、金銭の支払いを求められたり、危険な仕事に誘われることもあります。
また、コンピューターウイルスを仕込まれてデータを破壊されたり、秘密情報を奪われることもあります。
ロマンス詐欺
年齢、性別、社会的地位や収入などを偽り、言葉巧みに相手を信頼させ好意を抱かせ、外国に行って結婚するためにお金が必要だと、どうしても困っていてお金が必要だ、などと偽って支払いをさせます。
詐欺をした者は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。しかし、被害を受けた財産はほとんど戻ってきません。
オンラインカジノ
カジノが合法の国もありますが、日本では競馬など認可を受けた賭け事以外は、賭博罪に当たります(刑法第185条。50万円以下の罰金)。
無料版は賭博に当たらないとして、CMも出ていました。無料版から初めて、そこから有料版に手を付けると、賭博をしてしまった事になってしまいます。
トクリュウ・闇バイト
オンラインゲームなどで知り合い、儲かる話があるなどと言われて外国に行き、犯罪組織に捉われ、特殊詐欺などに加担させられてしまう事例が見られます。
前述のロマンス詐欺のほか、オレオレ詐欺などの特殊詐欺もさせられます。無理やりやらされたとしても、自分自身が犯罪者となってしまいます。詐欺のほか、窃盗(刑法第235条。10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。)や強盗(刑法第236条第1項。5年以上の有期拘禁刑)に該当する行為に加担させられることもあります。
不正アクセス
DMや他のSNSに繋がってより親密になったところで、言葉巧みにアカウント情報を出させたり、クレジットカードなどの情報を聞き出すこともあります。聞き出すだけでなく、コンピューターウイルスを仕込んだりして、勝手にパスワードなどを盗み出すこともあります。
他人のIDやパスワードを使って勝手にログインするような行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)の「不正アクセス」に当たります(同法第2条第4項)。
不正アクセス行為をすると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(不正アクセス禁止法第3条・第11条)。
不正アクセスをするだけでなく、そのためにパスワードなどを取得したり(同法第4条)や、他人に提供すること(同法第5条)、保管したり(同法第6条)、アクセス管理者になりすましたりアクセス管理者と誤認させてパスワードなどの入力を要求すること(同法第7条)も、禁止されています。これらの違反行為をすれば、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第12条第1号乃至第4号)。
人身取引
前述の詐欺などに加担されるだけでなく、借金をさせられて、監禁され居場所を制限され、著しく低い対価で売春などをさせられることもあります。
監禁(刑法第220条。3月以上7年以下の拘禁刑)、人身売買(刑法第262条の2第1項。3月以上5年以下の拘禁刑)や被略取者等所在国外移送(刑法第262条の3。2年以上の拘禁刑)などに当たります。
まとめ
このように、オンラインでは、国をもまたいだ、様々なトラブルに遭遇する恐れがあります
国際的なネットトラブルに遭いお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
プラットフォーム

情報流通プラットフォーム対処法は、正式には「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」と言います。
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が2024年に改正され、2025年4月1日に施行されました。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとされております。
改正のポイントは、大規模プラットフォーム事業者・大規模特定電気通信役務提供者に対して、権利侵害等に対して具体的措置を行う義務を負わせていることです。
インターネット上の誹謗中傷の書き込みを迅速に削除させる体制を整えることを目的としております。
法律が施行されることにより、大規模プラットフォーム事業者による削除対応が促されることになると思われます。
大規模特定電気通信役務提供者は、総務大臣が指定することになります。
発信者の数が多く、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるものを提供する者が指定されます。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする被侵害者が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。
侵害情報調査専門員の数は、決められた基準以上の十分な人数でなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、迅速に結果を申出者に通知しなければなりません。
大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く通知等の措置を講じなければなりません。
実施状況等については、毎年1回、公表しなければなりません。
インターネットトラブルに会ったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回相談は無料ですので、03-5989-0996へお気軽にお電話ください。
こちらの記事もご覧ください
SNSで中傷されたら

FacebookはアメリカのMeta社が運営する世界最大の実名登録制SNSです。
2004年に当時ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg)によって運営が開始されました。
アメリカ合衆国カリフォルニア州メンローパークに本拠地が置かれております。
世界の月間アクティブユーザー数は約30億人もいます。
日本でも月間アクティブユーザー数が約2600万人います。
実名で登録するのが原則で、リアルな人間関係が反映されるのが特徴です。
Facebookでは実名での利用者が多いですが、それでも誹謗中傷が行われることがあります。
Facebookで誹謗中傷の被害に遭ったら、削除請求や損害賠償請求を検討することになります。
削除請求で最初に考えられるのは、Facebookから直接削除依頼をすることです。
個別の投稿について問題を報告し、送信することができます。
これにより、Facebookが投稿を削除することがあります。
Facebookのガイドラインに違反していると判断したうえで、削除されることになります。
悪質なものに関しては、アカウント自体が削除されることもあります。
しかし、報告したからといって、Facebookが必ず削除するとは限りません。
報告しても、そのまま時間が経過して長期間放置される可能性もあります。
そうすると、更に被害が拡散してしまいます。
誹謗中傷の投稿をした相手にダイレクトメッセージを送って直接削除請求をすることは、慎重に判断するべきです。
相手がヒートアップし、更に誹謗中傷してくる可能性があります。
一旦は削除に応じても、再度誹謗中傷の投稿をしてくる可能性があります。
そこで、裁判所に訴えることを検討することになります。
弁護士を立てて、裁判所に削除を請求することになります。
損害賠償請求を含めて法的手段を取るのであれば、発信者情報開示請求を検討することになります。
Facebookは実名ユーザーが多いですが、なりすましの可能性もあります。
裁判所での手続きを通じて、相手の名前や住所等の身元をきちんと調べて特定する必要があります。
プロバイダ責任制限法を根拠として発信者情報開示請求をするのですが、最近は法改正によりこの手続きがしやすくなった発信者情報開示命令制度が出来ました。
また、損害賠償請求をするのであれば、削除されてしまうと証拠が消えてしまうので、その前にスクリーンショット等で証拠を残しておく必要があります。
このスクリーンショットも慎重に対応しなければならず、URLも含めて証拠として保存できなければなりません。
Facebookで誹謗中傷を受けたと感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に申し込みをしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全平穏な社会生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームがあります。
ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
インターネット関連で「訴えられた」「不祥事が発覚した」「被害に遭った」など急な出来事でどのような対応をとればよいのか不安がある方や、コンプライアンス体制を見直して不祥事・犯罪を未然に予防したいという法人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽に申し込んでください。
こちらの記事もご覧ください
ネットでの名誉棄損
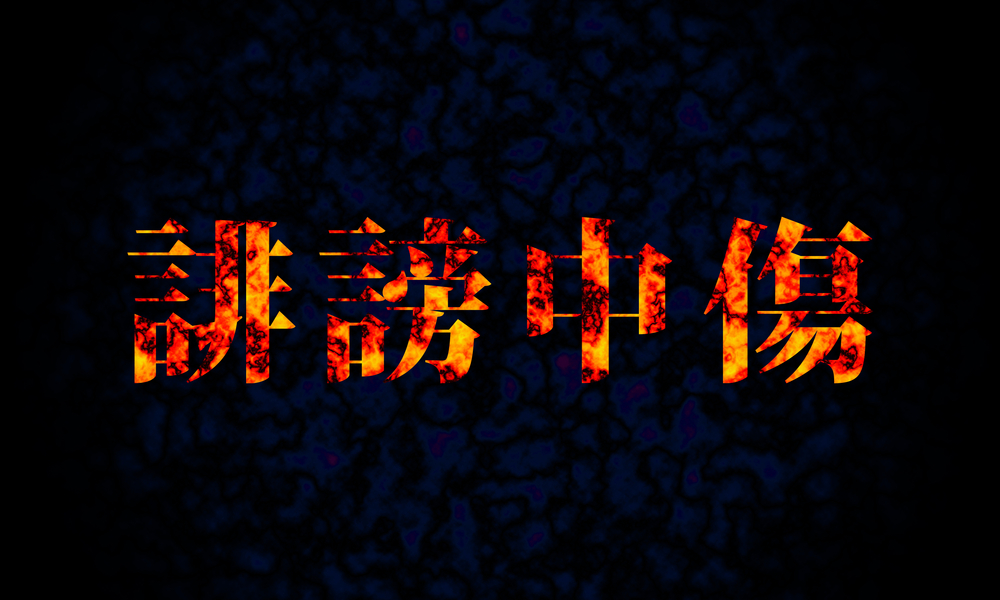
インターネット上で誹謗中傷を受けたとき、削除請求や損害賠償請求をする前提として、名誉毀損が成立するかが問題となります。
名誉とは、人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことをいいます。
公然とインターネット上で人の社会的評価を低下させる事実の適示の書き込みをしたら、名誉毀損として、民法上の不法行為が成立し、損害賠償の対象となります。
適示された内容が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとされております。
対象者が特定されていることも必要ですが、実名が記載されていなくても他の記載も含めて全体として誰のことを言っているのかが判断できる状況であれば問題ありません。
しかし、名誉毀損が例外的に成立しない場合があります。
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、当該情報が真実であるか、又は発信者が真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、名誉毀損は成立しません。
この公共性、公益性、真実性・相当性の3つが全て認められたら、名誉毀損は成立しません。
公共の利害に関する事実は、人の犯罪行為であったり、公的人物による社会的活動等があります。
特に政治家であれば広く範囲に含まれやすくなりますが、それでも純粋に私的な行為であれば公共性が認められにくくなります。
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合は、記事の内容・文脈等外形に現れているところだけによって判断すべきことではなく、その表現方法、根拠となる資料の有無、これを取り扱うについての執筆態度等を総合し、それが公益目的に基づくというにふさわしい真摯なものであったかどうかの点や、更には記事の内容・文脈等はどうあれ、その裏に隠された動機として、例えば私怨を晴らすためとか私利私欲を追求するためとかの、公益性否定につながる目的が存しなかったかどうか等の、外形に現れていない実質的関係をも含めて、全体的に評価し判定すべき事柄とされています。
特定個人に関する論評について、人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、名誉毀損が成立することになります。
内容が真実であれば、違法性がありません。
真実と信じるに足りる相当の理由がある場合は、故意や過失が認められません。
このように、名誉毀損が成立するかは非常に判断が難しい側面があります。
名誉毀損を受けたと感じたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談に申し込みをしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全平穏な社会生活を取り戻すお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームがあります。
ネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
インターネット関連で「訴えられた」「不祥事が発覚した」「被害に遭った」など急な出来事でどのような対応をとればよいのか不安がある方や、コンプライアンス体制を見直して不祥事・犯罪を未然に予防したいという法人の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽に申し込んでください。
こちらの記事もご覧ください
不正アクセス

インターネットが発達し、もはや対面でなくとも様々なサービスを提供したる受けることは当たり前になりました。一方で、他人のアカウントに成りすましてサービスの提供を受けたり、管理者と偽って企業のサーバーにアクセスして顧客情報を抜き取ることも行われるようになりました。サービスの提供や個人情報を集めている企業としては、自社の従業員等が他社に不正アクセスしないように注意する必要がありますし、自社の情報が不正アクセスをされないようにする必要があります。不正アクセスに対する十分な対策をせず、顧客の秘密情報などが漏れた場合、企業が責任を負わなければならない可能性があります。
ここでは、不性アクセスについて解説します。
不正アクセス
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)は、不正アクセス行為を禁止しています(同法第1条)。
この法律において「不正アクセス」とは、次のいずれかに該当する行為と定められています(同法第2条第4項)。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
典型的なのがIDとパスワードを入力してアクセスできるところに、許可なく他人のIDとパスワードを入力してアクセスする場合です。
なお、パスワードは「識別符号」(同法第2条第2項)のうちの「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号」(同項第1号)に当たりますが、パスワードだけでは意味がないので、IDが「その他の符号」として、IDとパスワードで「次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの」として「識別符号」に当たります。
何人も、不正アクセス行為をしてはなりません(不正アクセス禁止法第3条)。これに違反すれば、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(同法第11条)。
不正アクセス行為の用に供する目的で他人の識別符号を取得すること(同法第4条)や、業務その他正当な理由による場合でなく他人の識別符号をアクセス管理者や利用権者以外の者に提供すること(同法第5条)、不正アクセス行為の用に供する目的で不正取得された他人の識別符号を保管すること(同法第6条)、アクセス管理者になりすましたりアクセス管理者と誤認させて識別符号の入力を要求すること(同法第7条)も、禁止されています。これらの違反行為をすれば、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(同法第12条第1号乃至第4号)。
このような不正アクセスを行い相手方に損害を発生させれば行為者自身が相手方に対し損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。また、自社の従業員が自社の事業の執行に関して行えば、企業自身もこれにより発生した損害を賠償しなければなりません(民法第715条第1項)。
不正アクセスの防止のための措置
自社が不正アクセスを受けた場合、自社が被害者となりますが、企業が不正アクセスの防止のために必要な措置をとっておらず、これにより顧客の秘密情報が漏洩するなどの被害が発生した場合、企業自身の社会的信用を失い、また企業が顧客に生じた損害を賠償しなければならない事態になりえます。企業自身も不必要なサービスを排除したり、アカウントを厳重に管理し、ファイアウオールなどの侵入防止体制を導入するなど、不正アクセスを防止する手段を講じる必要があります。
参考
総務省:不正アクセスによる被害と対策
まとめ
インターネットに接続してサービスを提供する企業としては、このような不正アクセスを受けないようにする必要があります。
不正アクセスでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
ネット上のなりすまし対策ーネットのなりすましに対して,損害賠償請求をすることができるのか
« Older Entries