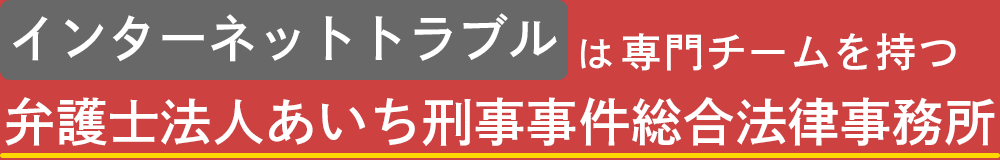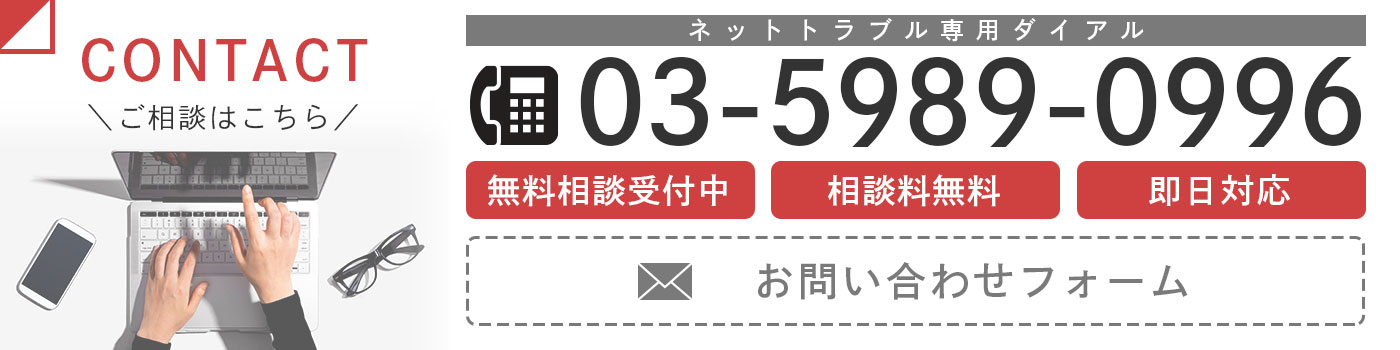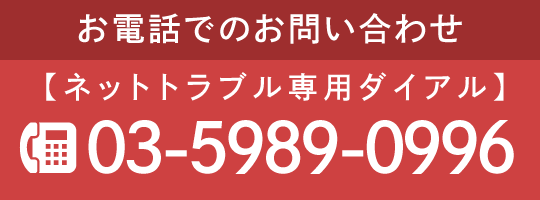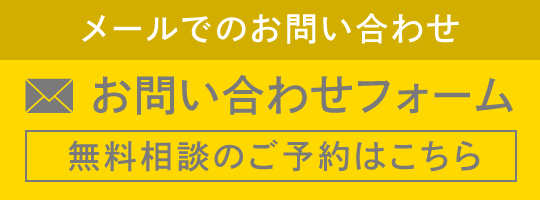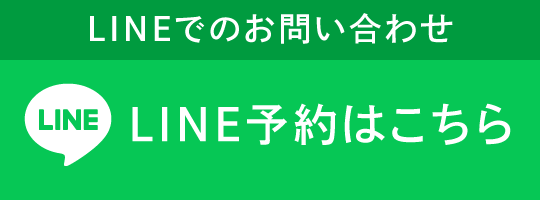Archive for the ‘ネットトラブル’ Category
インターネット上のなりすまし被害の対策ー最高裁令和6年12月23日判決を解説

インターネットのなりすまし被害が深刻になっています。
これにたいして、なりすましを行った人物についての発信者情報開示などの対策が考えられます。
このようななりすまし被害対策に関して、最近興味深い判決が出たので紹介します。
【事件の概要】
インスタグラムで,なりすましの被害を受け,自身の性的な投稿をされた人(原告)が,なりすましを行った人物の特定のために,経由プロバイダ(被告)に対して,なりすましを行った人物のIPアドレスに関して,なりすましを行った人物の氏名,住所,電話番号,メールアドレスといった発信者情報の開示を求める事件です。
なお,成りすました人物はすべて同一人物であることが判明しています。また,なりすました人物による投稿は令和3年4月29日に行われ,この投稿以後の成りすました人物によるログインは,令和3年5月20日から令和3年6月13日まで8回の行い行われています。
原審では,なりすました人物による8回のログイン全てについて発信者情報開示が認められましたが,これについて,プロバイダ側から、不服であるとして,上告されました。
【最高裁の判決】
最高裁は,本件各ログインがプロバイダ責任法5条2項の「侵害関連通信」に該当するかについて,以下のように判断しました。
原稿のプロバイダ責任制限法5条2項の「侵害関連通信」については,発信者情報の開示ができるところ,この侵害関連通信に該当するためには,プロバイダ責任制限法施行規則5条柱書の「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当しなければなりません。
そのうえで,ログイン通信それ自体については権利侵害性を有しないこと,しかし,ログイン通信について一切発信者情報の開示を認めないと,被害者の救済が不十分になることから,通信者等のプライバシー,表現の自由及び通信の秘密との均衡をふまえて開示されるべきであるとして,「施行規則5条柱書が侵害関連通信を『侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの』としたのは,同条各号に掲げる符号の電気通信による送信それぞれについて,開示される情報が侵害情報の発信者を特定するために必要な限度のものとなるように,個々のログイン通信等御侵害情報の送信との関連性の程度と当該ログイン通信等に係る情報の開示を求める必要性とを勘案して侵害関連通信に当たる者を限定すべきことを規定したものであると解される。」と法解釈しました。そのため,時間的近接性以外に個々のログイン通信と侵害情報の送信との関連性の程度を示す事情が明らかでない場合については,侵害情報の送信と最も時間的に近接するログイン通信が「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当し,それ以外のログイン通信については,あえて当該ログイン通信に係る情報の開示を求める必要性を基礎づける事情があるときにこれに当たり得ると基準を示しています。
その上で,権利侵害投稿が行われた後の21日後にされた本件ログインが,最も時間的に近接するためこの一つのルグイン情報について,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に該当すると判断しました。
それ以外の7件のログインについては,あえて開示すべき必要性が見つからないため,「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に当たらないと判断しました。
そのため,最高裁は,発信者情報開示請求のあった8回のログインのうち1回についてログイン情報の開示を認め,それ以外のログイン情報については,開示を認めませんでした。
【解説】
このように,名誉毀損の投稿そのものではなく,なりすまし被害についての発信者情報開示を求める場合,ログイン情報が権利侵害投稿を行った人を特定するカギになってきます。
しかし,ログイン情報というのは,名誉毀損などの権利侵害情報が含まれているものではないので,普通は開示することができません。しかし,なりすまし被害に関する場合に限っては,成りすました人物による権利侵害投稿と関連性がある範囲で開示が認められます。
この権利侵害投稿と関連性があるといっても,全てのログイン情報を開示すると弊害が大きいことから,必要な範囲でのみ開示を認めるということになります。
そのため,今回の最高裁の事例の場合,権利侵害投稿から最も近接した時間のログイン情報だけが開示されました。
ただし,今回の最高裁判所の事例の場合,なりすましを行っている人は一人で,複数の人によるものではなかったので,時間的に最も近接した時点でのログイン情報の開示が認められたという事情があります。
そのため,なりすましを行っている者が複数人である場合,時間的に最も近接した時点以外のログイン情報の開示が認められる可能性があります。
そのため,なりすまし被害があった場合には,ログイン情報の開示請求を行い,なりすましによる権利侵害表現から最も近接した日時のログイン情報の開示を求める形で発信者情報開示請求を行うことになります。
なりすまし被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説
インターネット上のレビューの削除ーAmazonのレビューの削除事例をもとに解説

インターネット上のレビューの削除
通信販売などで商品のレビューをする機能があります。ほかのユーザーの参考になりますし、事業者もこのレビューを参考に新たな商品開発をしていきます。
一方で、ただ誹謗中傷をしたり事実に基づかない記載をされることもあります。このようなレビューは削除することを検討するべきです。
ここでは、Amazonのレビューの削除の事例をもとに解説します。
【事例】
Aさんは小説家で,アマゾンで本が出品されて販売されています。
ある日,小説の商品レビューに,「★1 こちらを通勤の際に時間があったので読んでいたのですが,全くの時間の無駄でした。妄想も甚だしい内容で,何一つ面白くありません。作者の住所は(実際の住所)なので,ここに何百通も苦情を送りたくなりました。」と書かれていました。
そのため,このアマゾンのレビューの削除を考えるようになりました。
このような場合に,アマゾンのレビューを削除できるか解説します。
Amazonレビューの削除方法
Amazonのレビューの削除方法は大きく分けて二つあります。
①Amazonに削除依頼を請求する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求する方法です。
Amazonに削除依頼を行う方法
複数のルートがあるようです。
(1)商品ページのレビュー欄から行う方法
商品ページの問題のレビューにある「レポート」をクリックして,レポートを報告する理由を選択します。
その後,商品レビューが削除されるのを待って,解決するという方法があります。
(2)Amazonに対して,削除依頼書を郵送する方法
Amazonジャパンに削除依頼書を郵送することで商品レビューの削除を求める方法です。
この削除依頼書を郵送する場合,どこにレビューが掲載されているのか,そのレビューの内容は何なのか,それによって,どのような権利が侵害されるのかということを記載して,郵送することで解決することができます。
そのさいの郵送先は,
アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
に郵送するとよいことになっています。
裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
このように,削除請求を行っても,Amazon側が削除を行わない場合,裁判所に対して,削除仮処分を行うことになります。
Amazonは日本国内に法人がありますので,「アマゾンジャバン合同会社」を被申立人として,仮処分を行うことができます。
そのため,アマゾンジャパン合同会社を被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定して主張して,権利侵害が大まかに認められれば,簡易・迅速に投稿されたレビューの削除を行うことができます。
今回の【事例】のような場合,アマゾンのレビューに作者の個人情報である住所が書かれていますので,プライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。また,作者に対して,何百通もの苦情を送るということが書かれているため,脅迫を行っているということも出来ます。
そのため,脅迫またはプライバシー権侵害を理由に削除請求を行うことができます。
このような手続で書き込みの削除を請求することができますので,迅速に弁護士に依頼することをお勧めします。
インターネットのレビューにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
インターネットのブログの削除ーSeesaaブログの削除の事例をもとに解説

インターネットには記事のほか、有志によるまとめ記事やwikiなども数多くあります。しかし、このようなサイトでも個人のプライバシー情報が載せられたり、誹謗中傷が行われることがあります。
ここでは、Seesaaブログ(wiki,SSブログ)に投稿された記事の削除の事例をもとに解説していきます。
【事例】
Aさんは,5年前にとある県の飲食店に侵入し,手提げ金庫を奪ったという罪で逮捕されました。その当時,ニュースでは,『飲食店に侵入し現金の入った手提げ金庫を奪ったA(実名)が逮捕されました。調べに対して,Aは「やってません」「人違いです」と容疑を否認しています。』と報道されました。しかし,警察や検察での捜査の結果,Aさんではない可能性が出てきたため,不起訴になりました。
そのため,報道各社のニュースや当時の新聞記事に関するネットニュースは消去されましたが,あるブログで,「飲食店に侵入したドロボウA逮捕」とのタイトルとともに,Aさんについての当時のニュースをコピペし,最後に,『こんなヤバい奴がいるとか治安悪過ぎ,「やってない」とかそういう言い訳通用しないだろ,とっとと刑務所に行くことをお勧めする。』と書かれています。
そのブログは,Seesaaブログの記事として書かれているものでした。
このような場合に,Aさんが,どのようにして,記事の削除を請求することができるのか解説します。
削除請求を行う方法として,大きく,①Seesaaブログのお問合せフォームから削除依頼する方法,②裁判所に申し立てを行い,削除請求をする方法があります。
Seesaaブログのお問合せフォームを使う方法
「Seesaaブログに関するお問い合わせ」というページに,名前,削除対象のブログ,お問合せ内容を書くことで,削除させることができます。
この削除請求を行う際のフォーマットは決まっているようで,Seesaaサービスサポートのご案内の「その他利用規約違反と思われる行為が合った場合」のページによれば,
通報種別に「その他」と指定し,お問い合わせをしている人の名前を入力し,メールアドレスとSeesaaサービスのアカウントについて入力し(Seesaaサービスのアカウントを取得していない場合は,「未取得」と記載すること),利用規約違反の種別,被害の状況について記入することになるようです。
これらを記載し,Seesaaに送信し,削除されるのを待つことによって,記事の削除を行うことができます。
あくまで,Seesaa側に削除請求を求める方法ですので,Seesaa側で,削除する必要は無いと判断すれば,削除されないということもあります。
裁判所に申し立てを行い,削除請求を行う方法
Seesaaブログに削除請求を行ったにもかかわらず,Seesaa側で削除が行われない場合,裁判所に削除申し立てを行い,削除請求を行うことが考えられます。
Seesaaブログの運営会社は,2024年1月1日に株式会社ファンコミュニケーションズへの吸収合併があったことから,現在は,株式会社ファンコミュニケーションズが運営しています。
そのため,株式会社ファンコミュニケーションズを被申立人として,どのような投稿から,どのような権利が侵害されたのかを特定し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易迅速な手続によって,削除が認められます。
今回の【事例】のような事件の場合,不起訴になった犯罪事実についての書き込みがされていますので,名誉権侵害がされているということができます。
そのため,今回のような事例の場合,Seesaaブログや運営会社に対して,ブログの削除を請求することができると考えられます。
このような手続でブログの記事の削除をすることができると考えられますので,名誉毀損に当たるようなブログの記事でお困りの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
ブログ記事にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の方法

インターネットは、今や、人と人をつなぐインフラになっており、インターネットとかかわらずに生活する方が困難になっています。
一方で、インターネットの影響力の大きさから、インターネット上での誹謗中傷・名誉毀損の記事の書き込みが社会問題となっております。
個人が簡単に書き込んだ悪意のある記事により、被害者は大きな被害を受けることになります。
インターネット上で誹謗中傷・名誉毀損の記事を書かれたら、削除を求めていくことになります。
記事がインターネット上に残り続けて時間が経過するほど、記事の情報が拡散して被害が更に大きくなります。
迅速な対応が必要になりますが、削除請求の方法としては、複数あります。
ホームページに削除請求依頼のフォームやメールが存在している場合があります。
そのフォームやメールから、記事の削除請求をすることになります。
簡易迅速に請求することができ、ホームページ側も早めに削除の対応をしてくれることがあります。
まずはこの任意での削除請求方法を検討することになります。
しかし、サイト側の裁量で削除するかしないかを判断されるので、状況次第ではすぐに削除してくれない場合があります。
個人で削除請求する場合、しっかりとした根拠に基づいて適切に削除請求の主張を行うことは難しいです。
そこで、弁護士を通じて削除請求をすれば、根拠をもって主張内容を整理してサイト側に伝えることができるので、個人で請求するより早く削除請求に応じてもらえる可能性が高まります。
弁護士から請求されたという事実から、請求を受けた側はきちんと削除請求に応じなければならないという心境になる可能性が高まります。
掲示板サイトによっては、弁護士からの削除請求の専用窓口を設けている場合もあります。
この方法では、削除については応じてくれるけれども、記事を書きこんだ人物の情報を伝えてはくれません。
一般社団法人テレコムサービス協会ではガイドラインが作成されており、このガイドラインに従った削除請求をすることができます。
https://www.telesa.or.jp/consortium/provider/index.html
サイト管理者等に削除依頼書を郵送したら、サイト管理者等は発信者に対してその書き込みの削除の可否を問い合わせます。
発信者から反論が無ければ削除されることになります。
発信者から反論があった場合には、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の有無をサイト管理者等が判断することになります。
削除依頼書の書き方が専門的であり、弁護士を通じて作成した方が上手くいくと思われます。
任意での請求では削除に応じてもらえない場合は、裁判での削除請求を検討することになります。
迅速に削除を実現させるために、記事の削除を求める仮処分の申立てを利用する方法があります。
正式な裁判を経なくても、裁判所の仮処分命令を受けた管理者は、それに従い記事の削除に応じる場合が多いです。
損害賠償請求のために、発信者情報開示請求訴訟を提起することもあります。
裁判の過程で、円満に示談となり、記事が削除されることもあります。
裁判手続きは弁護士に依頼して対応することになります。
費用と時間がかかりますので、最後の手段とはなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、削除請求の知識経験が豊富な弁護士が所属しております。
元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、誹謗中傷・名誉毀損記事の削除請求の最適な解決策をご提案し、会社利益や個人の平穏な生活を守ります。
全国展開している法律事務所だからこそできるネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
初回の面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください
マッチングアプリであった人に訴えられたー出会い系サイト・マッチングアプリでのトラブルについて解説

最近,性交渉目的の出会い系サイトやマッチングアプリで知り合った異性と金銭の授受のある性交渉を行い,後で「レイプだった」と言われたという事件が多く見られますので,解説していきます。
【事例】
事件を基にしたフィクションです。
Aさんは,甲という性交渉目的の出会いを目的とするマッチングアプリを利用し,Bさんと「1万円でマッサージをお願いします」(マッチングアプリの利用者間では「1万円でセックスをお願いします」という約束になることが暗に決まっている)という約束でラブホテルで出会い,1万円を渡して性交渉(暴行脅迫は無い,Bさんが睡眠中であったなどの事情も無い)をしました。
後日,警察から「マッチングアプリで知り合った人と出会い,レイプされましたとの被害届が出されています」との連絡を受け,Bさんに連絡を取ったところ,「あれはレイプだった,アプリも性交渉は許していないし,私も精神的苦痛を被った。1000万円払って,そしたら,被害届を取り下げるから」と言われました。
ただし,Aさんは逮捕されていません。
このような場合に,①どのような犯罪が問題となるのか,②弁護人はこのような事件にどのように対応するのかについて解説していきます。
問題となる犯罪
不同意性交等罪(刑法177条1項)
まず,不同意性交等罪の成立が問題となります。
不同意性交等罪が成立するためには,①刑法176条1項各号の事由かこれに類する事情が認められること,②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じていると認められること,③性交等を行うことが認められる必要があります。
見込まれる刑罰
仮に,不同意性交等罪が成立するとなると,5年以上の懲役刑が予定されています。
そのため,情状酌量になるような事情が無ければ,実刑となり,すぐに刑務所に行くことになります。
弁護人としての活動
そのため,弁護士としては,①示談をするか,②犯罪になるような事件であると認めず,不起訴になるよう供述をコントロールするということが大事になってきます。
今回のような事例の場合,
もちろん,①の手段を選択して,起訴される前に1000万円で示談を行い,起訴猶予を理由とした不起訴を目指すということも可能です。この場合に弁護人を選任する利益としては,これ以上の不当要求を拒めるという利益があります。
こういった事例の場合,弁護人をつけこれ以上の金銭要求を拒めるような示談を無い限り,被害者が1000万円支払ってくれたから,なんか理由をつけて,更に取れると思い,「精神科に通うための治療費として500万円」などと言い出し,示談金がかさんでいく可能性があります。
そのため,弁護人を選任し,これ以上の金銭要求を拒める形での示談を行うことによって,1000万円支払って事件を不起訴にし,これ以上の不当要求を拒んで事件を解決するということが考えられます。
②の手段を選択することも考えられます。
今回のような事例の場合,Aさんは,Bさんに対して暴行や脅迫を行っていないですし,Bさんの寝込みを襲ったような事情もありません。不同意性交等罪の刑法176条1項各号の要件を満たす事情がありません。そもそも,マッチングアプリのやり取り上,同意して性交に及んだとみられる事情があります。
そのため,Aさんが犯罪を否定した場合,それなりに認められる可能性があります。
そのため,弁護人としては,依頼者に対して,継続的なアドバイスを行って,性犯罪事件ではないという形で話させ示談も何もせずに,不起訴を目指すということが考えられます。
この手段を取る場合,被害者からの金銭要求を弁護士を使って拒むことができますし,弁護士から,継続的なアドバイスをもらって,警察官の取調べに対応でき,不起訴になる可能性を上げるというメリットがあります。
このような弁護人としての活動が出来ますので,このようなトラブルに巻き込まれた場合には,迅速に弁護士に相談して,事件についての解決を目指すということができます。
出会い系サイトやマッチングアプリでのトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐ法律について解説
SNS上の投稿の削除ーインスタグラムに投稿された投稿の削除について解説

インスタグラムなど様々なSNSが展開され、様々な人が情報を投稿できるようになりました。その一方で、他人のプライバシーに関する情報も安易に拡散される可能性が大きくなっています。
【事例】
Aさんは,お笑い芸人として,テレビに出演している芸能人です。
ある日,インスタグラムを見ていたところ,「Aさんに熱愛発覚!?」とタイトルが付けられ,彼女と自宅付近を歩いている様子が撮影されている写真を発見しました。
Aさんに彼女がいることは事実ですが,Aさんの顔と,プライベートの様子が撮影されているので,Aさんとしても,その点が気になっているようです。
写真の中身としても,Aさんと彼女の様子が大写しになっており,どちらにもモザイクがかけられていません。
このようなインスタグラムの投稿が見つかった場合に,投稿の削除をすることができるか説明します。
インスタグラムの投稿を削除する方法としては,
①インスタグラムで報告を行い,削除を求める方法と,②裁判所の仮処分によって,投稿の削除を求める方法があります。
以下,それらの方法について解説します。
インスタグラムで報告を行う方法
①インスタグラムの投稿からも直接報告できるのですが,インスタグラムの報告フォーム上,名誉権侵害やプライバシー権侵害についての項目はありません。強いて言えば,「いじめまたは嫌がらせ」の項目がこれに該当することになります。
そのため,インスタグラムの問題の投稿について,「…」を押し,「報告する」を押し,「いじめまたは嫌がらせ」を選択することによって,対応することになります。
②しかし,①の方法では,なぜ削除されるべきなのか明らかではないため,メタ社が対応しない可能性があります。そのため,インスタグラムのページの下部にある「利用規約」のページから,Instagramの「ヘルプセンター」のページにアクセスします。
③「ヘルプセンター」の「プライバシー,セキュリティ,報告」から「報告するには」を選択して,「Instagramでの嫌がらせやいじめの報告」を選択します。
④その中に青字で「報告」と書かれているところを押します。すると,インスタグラムのヘルプセンターのページが表れるので,アカウントを持っているかどうか,報告しようとしているコンテンツの閲覧がブロックされているか聞かれるので,入力します。
⑤報告したい投稿のリンクを貼り,その投稿が不適切な理由として,プライバシー権を侵害しているなどの詳細な理由を書き,報告し,削除することを求めることになります。
(なお,「Instagramのアカウントを持っていますか」に「はい」と答え,「報告しようとしているコンテンツの閲覧がブロックされていますか」に「いいえ」と答えると,直接投稿を報告するよう促されてしまうので,「Instagramのアカウントを持っていますか」という質問に対しては「いいえ」と答えることをお勧めします。)
裁判所の仮処分によって,投稿の削除を求める方法
インスタグラムの運営会社であるメタ社に対して,投稿削除の仮処分を行うことが考えられます。
インスタグラムの運営会社はアメリカ合衆国のカリフォルニア州に本社を置く会社ですが,日本にも法人があること,損害が日本で発生していると考えられることから,日本の裁判所に訴えを提起することによっても裁判を行うことができます。
そのため,メタ社を被申立人として,どのような投稿から,権利侵害が行われたのか特定して主張し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された書き込みの削除を行うことができます。
今回のAさんの事例の場合,インスタグラムにプライベートの情報である彼女といる状態の写真が投稿されていること,しかも,顔も隠さずに投稿されていることから,プライバシー権,肖像権が侵害されていることを理由として,インスタグラムで報告を行ったり,メタ社を被告として,投稿削除の仮処分を求めることになると考えられます。
このような手続で投稿の削除を行うことができますので,プライバシー権侵害,肖像権侵害でお困りの方は,弁護士に相談することをお勧めします。
SNSへの投稿でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
ネットでの性被害

インターネットの発達により、世界中の人が繋がることができるようになりました。特にSNSの普及で、気軽に他の人と繋がることができるようになりました。
一方で、性的な映像を簡単に目にするようになり、また他人に送ることも容易になりました。また、マッチングアプリなどで人と会うことも便利になりましたが、その一方で性犯罪に遭ってしまう恐れも高まりました。このため、世界中で青少年の性被害が多発しています。
ここでは、日本における性被害防止のための法律について解説します。
16歳未満の者に対する面会要求等罪
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。例えば、14歳の相手に対し17歳の者が行為した場合は含まれません。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
① 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
② 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
③ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
この罪を犯した上で、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
また、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限ります。)を要求した者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、第1項の犯罪と同様、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります。)は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
① 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
② 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
児童ポルノ
18歳未満の児童(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法第2条第1項)について、写真のほか、画像データなど「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物」であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものが児童ポルノに該当します。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
18歳未満の児童のものと知って性的な画像をダウンロードしたりすれば、児童ポルノの所持に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第1項)。この児童ポルノを電子メールで他人に送るなどの提供をすれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第2項)。、ます。児童に裸の画像を取って送らせるなど性的な画像の作成に強く関与したのであれば、児童ポルノ製造に該当し、同様に3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(児童ポルノ法第7条第4項)。SNSに挙げるなど、不特定多数に提供した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処され、又はこの両方を科されます(児童ポルノ法第7条第6項)。
青少年健全育成条例
各都道府県の青少年健全育成条例では、青少年に児童ポルノなどの提供を求める行為や下着の買受などを禁止ししています。
東京都の青少年の健全な育成に関する条例では、次のように定め、児童ポルノや下着等の提供を求めることを禁止しています。
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第十八条の七 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
第18条の7の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第7号)。
第15条の2第1項の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処されます(第26条第1項第4号)。これを業として行っていた場合は、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。
第15条の2第2項の規定に違反した場合、50万円以下の罰金に処されます(第24条の4第1号)。
まとめ
このように、様々な法律で青少年を性被害から保護しています。
インターネット上での性被害にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
インターネット上のトラブルーインターネットを利用するなかで遭遇するおそれのあるトラブルについて解説
インターネットと名誉毀損ー名誉毀損罪の犯罪が成立するか

インターネットトラブルの事件において、刑法上の名誉毀損罪が成立するかの判断は重要です。
刑法上の犯罪が成立するのであれば、警察に被害届・告訴を提出し、状況次第では犯人が逮捕されることになります。
犯人が逮捕されたら、犯人側から謝罪や被害弁償の話をすることを求めてくることがあります。
今回は、刑法上の名誉毀損罪について解説いたします。
刑法第230条第1項には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
人が円滑な社会生活を送るためには、人の名誉を保護しなければなりません。
社会が与える評価としての外部的名誉・社会的名誉が保護されます。
名誉を人に対する社会の評価という事実的なものとして捉えております。
公然とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいいます。
公然性は、現実に認識することを必要とせず、認識できる状態に置かれていれば足ります。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
非公知の事実に限らず、公知の事実でも、摘示によって更に名誉を低下させるおそれがあれば認められます。
真実であっても認められ、虚偽の事実である必要はありません。
事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価は含まれません。
誰に対する事実の摘示であるかが明らかになっていなければなりません。
対象となる人は、法人その他の団体も含まれます。
名誉毀損行為としては、人の社会的評価を害するに足る行為があればよく、現実に害されることは必要ではありません。
他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る方法で摘示することについての故意が必要になります。
刑法第230条の2では、「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定されております。
本条は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法第21条による正当な言論の保障との調和を図ることを目的としております。
公共の利害に関する事実とは、社会一般の利害に関係することをいい、公共性のある事実を評価・判断するための資料になり得るものであることをいいます。
そのため、私生活上の事実であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、公共の利害に関する事実に該当することがあります。
政治家や公務員やその他の社会的地位がある人であれば、認められやすくなります。
目的の公益性は、その事実を摘示した主たる動機・目的が公益を図ることにある場合をいいます。
真実の証明が出来たら、犯罪は成立しません。
真実の証明が出来なくても、事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、故意がないとして犯罪は成立しません。
インターネット上で名誉毀損の被害を受けたら、弁護士に相談してください。
具体的にどのような方法で対応していくべきか、丁寧に説明させていただきます。
時間が経てば経つほど被害は拡大していきますので、なるべく早いご相談をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料の面談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
インターネットトラブルについて強い弁護士が懇切丁寧に対応させていただきます。
こちらの記事もご覧ください
インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください
ネット上のコメントの削除ーニコニコ動画のコメントの削除

【事例】
Aさんは,ニコニコ動画で自分の作詞作曲した音楽をボーカロイドに歌わせた動画を配信している動画投稿者です。
ある日,Aさんが自身の作詞作曲した曲の動画のコメントを見ていたところ,0:40くらいに「これ俺の曲のパクリだろ」と赤文字で表示され,直後に「コレ→sm22222222」そこから,継続的に「パクリ」「パクリ」動画が見にくくなる程流れるようにされていました。
しかし,Aさんとしても,この曲の動画を見たことが無く,弁護士に相談しても,歌詞もメロディーも全然似ていないとの回答でした。
そのため,Aさんは,これらのコメントを削除したいと考えました。
このような場合に,ニコニコ動画でのコメントの削除の方法について解説していきます。
コメントを削除させる方法として,①ニコニコ動画の通報ボタンを使う方法,②裁判手続による方法が考えられます。
そのため,以下これらの方法について解説していきます。
ニコニコ動画の通報ボタンを使う方法
ニコニコ動画で通報機能を利用するためには,ニコニコ動画のアカウントを作成する必要があります。
そのため,
①ニコニコ動画のアカウントを作成すること,
②問題の動画の動画ページに移動し,動画視聴ページの問題となるコメントをクリックします。
③違反していると考えられる理由についての記載を求められるため,その理由を記載します。特に,ニコニコ動画のニコニコ利用規約とニコニコ活動ガイドラインのどこに違反しているかということを詳細な理由と共に記載すると,運営会社にとっても対応がしやすくなります。
このようにして,通報を行うことによって,ニコニコ動画のコメントの削除をすることができます。
ただし,ニコニコ動画側から,個別の通報に対する回答は行っていないので,削除されたのかどうかはもう一度動画を見なおさない限り分かりません。
裁判手続による方法の場合
通報したにもかかわらず,ニコニコ動画側からのコメントの削除が無い場合,裁判手続きによることになります。
裁判所の仮処分による場合,投稿記事削除の仮処分を行う方法に寄ることになります。
この手続は,名誉権あるいは,プライバシー権などが侵害されているとおおむね認められる場合,通常の裁判よりも迅速かつ,簡易な手続によって暫定的に投稿記事の削除を行わせるものです。
この判断については,裁判所に申し立ててから,1か月から2か月程度で結論が出るとされています。そのため,比較的迅速に記事の削除を行わせることができます。
この手続による場合でコメントの削除を求める場合,どのコメントなのかということについて,ユーザーID,コメント番号,コメント内容などから特定して,なぜそれが名誉権侵害となっているのかについて詳細な理由をつける必要があります。
この手続についてもノウハウのある弁護士に頼むことが望ましいです。
また,弁護士や,裁判所から見てどのような書き込みがどのような文脈で出てきたのか分かりやすくするために,書き込まれた記事のスクリーンショットを残しておくと望ましいです。
【事例】の場合の対処方法
この事例の場合,Aさんが著作権侵害を行っていないにもかかわらず,著作権侵害を行っていると言われていますので,名誉権を侵害されている事態が発生していると言えます。
そのため,ニコニコ動画の通報機能や,裁判手続を用いて問題のあるコメントを削除していくことになります。
動画のコメントでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説
ネット掲示板の書き込み削除ーしらたば掲示板に書き込まれた書き込みを削除したい

インターネットでは「掲示板」という様々な議題について書き込みができるサイトがあります。誰もが利用できる半面、以下のような悪質な書き込みがされることがあります。
【事例】
Aさんは,動画配信者として活動している人物です。
ある日,したらば掲示板のサイトをみていたところ,「Aアンチスレ」という掲示板群が立ちあげられていました。この掲示板の中の「【朗報】Aゲームが下手part53」で,「23 Aのゲームセンスゴミ過ぎ,絶対池沼」「31 >>23 その通り過ぎる。リスナーのと会話もかみ合ってねえし,健常じゃねえ。IQ70くらいで,中度くらいの池沼だろ。病院行けよガイジ」と書かれていました。
(「池沼」とは,「知的障碍者」を指し,「ガイジ」とは「障害者」を指す言葉で,どちらも差別的なネットスラングです。)
この場合に,このような書き込みの削除をどのように行うか解説します。
口コミの削除をどのようにするのか
口コミの削除の方法は,①したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法,②したらば社に削除依頼をする方法,③裁判所に申し立てを行い削除請求をする方法があります。
したらば掲示板の掲示板管理者に削除依頼をする方法
したらば掲示板は,レンタル掲示板を無料で作成できるサイトですので,個々の掲示板に掲示板管理者がおり,書き込みの削除を行う際には,掲示板管理者に連絡するという手段があります。
この場合,
①個々の掲示板の一番下にある「掲示板管理者へ連絡」をクリック
②掲示板管理者への連絡フォームのページが表示されるので,掲示板URL,名前とメールアドレス,質問の種類として「削除依頼」を入力します。そのうえで,質問内容の記入の欄に,問題と考えるスレッドのURL,レス番号,その書き込みが何権侵害になっているのかという詳細を書く必要があります。
③通常は,7日程度で返信があり,これによって,削除することができます。
もし,掲示板管理者が削除してくれない場合には,したらば社に削除依頼をするということができます。
したらば社に削除依頼をする方法
したらば掲示板の個々の掲示板の管理者が削除に応じてくれない場合,したらば社に削除依頼をする方法を検討することになります。
この方法によって,削除を依頼する場合は,
①「弁護士・法務関係,捜査関係のお問合せ」をクリックします。
②「弁護士の方」の方をクリックします。
③お問い合わせ内容として,「送信防止措置(削除)」「送信防止措置(削除).開示依頼」のどちらかを選択,該当スレッドのURLの入力,レス番号の入力,弁護士の事務所名,弁護士の名前,メールアドレスを入力します。
④内容の欄に,問題となる書き込みがなぜ権利侵害に当たるのかということを入力します。
⑤これによって,したらば社の担当者から追って回答する旨の連絡があり,追加の書面の提出などが求められ,掲示板の書き込みについて削除することができます。
なお,弁護士でなくとも,本人であれば削除依頼をすることはできるようです。
この方法によっても,したらば社が応じてくれない場合は,裁判所に申し立てを行う方法によって対応することになります。
裁判所に申し立てを行い,削除請求をする場合
したらば掲示板の運営会社については,株式会社したらばが運営会社になっています。
そのため,したらば社を被申立人として,どのような投稿から,権利侵害が行われたのか特定して主張し,権利侵害があると大まかに認められれば,通常の裁判より簡易・迅速に投稿された書き込みの削除を行うことができます。
今回の【事例】のような場合,掲示板の差別的な書き込みがされていますので,名誉権が侵害されていると考えられます。
そのため,今回の事例の場合,したらば掲示板の管理者やしたらば社への削除依頼,裁判所の仮処分によって,書き込みの削除を行うことができると考えられます。
このような手続で書き込みの削除を請求することが考えられるので,名誉棄損に当たるような内容の書き込みにお悩みの場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
インターネットの書き込みでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
誹謗中傷投稿の削除ーインターネット掲示板のスレッドや書込みの削除について解説
« Older Entries Newer Entries »