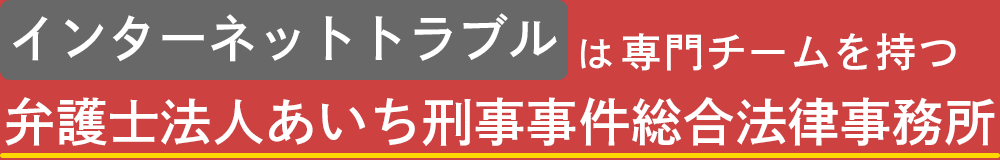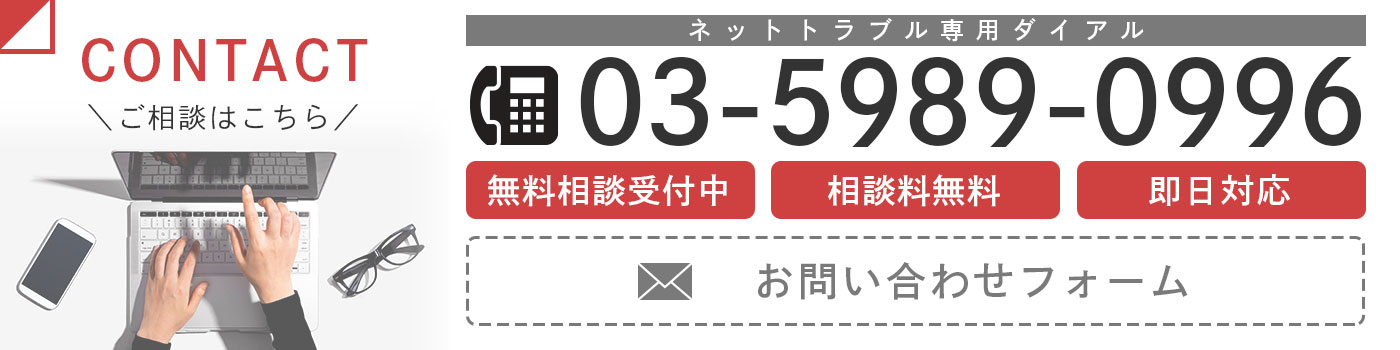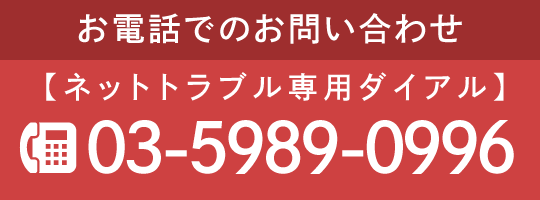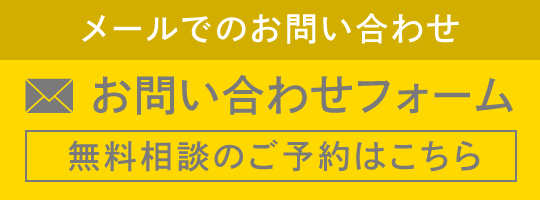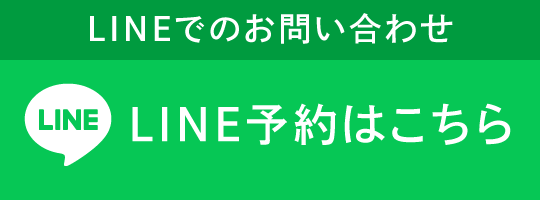Archive for the ‘損害賠償’ Category
マッチングアプリであった人に訴えられたー出会い系サイト・マッチングアプリでのトラブルについて解説

最近,性交渉目的の出会い系サイトやマッチングアプリで知り合った異性と金銭の授受のある性交渉を行い,後で「レイプだった」と言われたという事件が多く見られますので,解説していきます。
【事例】
事件を基にしたフィクションです。
Aさんは,甲という性交渉目的の出会いを目的とするマッチングアプリを利用し,Bさんと「1万円でマッサージをお願いします」(マッチングアプリの利用者間では「1万円でセックスをお願いします」という約束になることが暗に決まっている)という約束でラブホテルで出会い,1万円を渡して性交渉(暴行脅迫は無い,Bさんが睡眠中であったなどの事情も無い)をしました。
後日,警察から「マッチングアプリで知り合った人と出会い,レイプされましたとの被害届が出されています」との連絡を受け,Bさんに連絡を取ったところ,「あれはレイプだった,アプリも性交渉は許していないし,私も精神的苦痛を被った。1000万円払って,そしたら,被害届を取り下げるから」と言われました。
ただし,Aさんは逮捕されていません。
このような場合に,①どのような犯罪が問題となるのか,②弁護人はこのような事件にどのように対応するのかについて解説していきます。
問題となる犯罪
不同意性交等罪(刑法177条1項)
まず,不同意性交等罪の成立が問題となります。
不同意性交等罪が成立するためには,①刑法176条1項各号の事由かこれに類する事情が認められること,②同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じていると認められること,③性交等を行うことが認められる必要があります。
見込まれる刑罰
仮に,不同意性交等罪が成立するとなると,5年以上の懲役刑が予定されています。
そのため,情状酌量になるような事情が無ければ,実刑となり,すぐに刑務所に行くことになります。
弁護人としての活動
そのため,弁護士としては,①示談をするか,②犯罪になるような事件であると認めず,不起訴になるよう供述をコントロールするということが大事になってきます。
今回のような事例の場合,
もちろん,①の手段を選択して,起訴される前に1000万円で示談を行い,起訴猶予を理由とした不起訴を目指すということも可能です。この場合に弁護人を選任する利益としては,これ以上の不当要求を拒めるという利益があります。
こういった事例の場合,弁護人をつけこれ以上の金銭要求を拒めるような示談を無い限り,被害者が1000万円支払ってくれたから,なんか理由をつけて,更に取れると思い,「精神科に通うための治療費として500万円」などと言い出し,示談金がかさんでいく可能性があります。
そのため,弁護人を選任し,これ以上の金銭要求を拒める形での示談を行うことによって,1000万円支払って事件を不起訴にし,これ以上の不当要求を拒んで事件を解決するということが考えられます。
②の手段を選択することも考えられます。
今回のような事例の場合,Aさんは,Bさんに対して暴行や脅迫を行っていないですし,Bさんの寝込みを襲ったような事情もありません。不同意性交等罪の刑法176条1項各号の要件を満たす事情がありません。そもそも,マッチングアプリのやり取り上,同意して性交に及んだとみられる事情があります。
そのため,Aさんが犯罪を否定した場合,それなりに認められる可能性があります。
そのため,弁護人としては,依頼者に対して,継続的なアドバイスを行って,性犯罪事件ではないという形で話させ示談も何もせずに,不起訴を目指すということが考えられます。
この手段を取る場合,被害者からの金銭要求を弁護士を使って拒むことができますし,弁護士から,継続的なアドバイスをもらって,警察官の取調べに対応でき,不起訴になる可能性を上げるというメリットがあります。
このような弁護人としての活動が出来ますので,このようなトラブルに巻き込まれた場合には,迅速に弁護士に相談して,事件についての解決を目指すということができます。
出会い系サイトやマッチングアプリでのトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
インターネットでの性被害-青少年の性被害を防ぐ法律について解説
インターネットでの誹謗中傷への対策ーインターネット上で誹謗中傷を受けたら弁護士に相談してください

インターネットが誰でも使えるようになった一方で、インターネットを使った誹謗中傷が深刻になっています。この記事では、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の対応について解説します。
削除請求
インターネット上で誹謗中傷を受けた人は、削除請求をしていくことになります。
インターネットのSNSや掲示板サイトに、本人を特定できる名前などの個人情報が書き込まれ、悪口や根拠のない嘘を言われて誹謗中傷されることがあります。
インターネットでは誹謗中傷の記事が継続して残り続け、拡散していくことになります。
時間が経てば経つほど損害は大きくなるので、なるべく早く削除を実現しなければなりません。
名誉を違法に侵害された人は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止めを求めることができます。
削除請求は、まずは任意交渉による方法を検討します。
メールやオンラインフォーム等で請求していきます。
拒否されて任意では削除が実現できないのであれば、裁判に訴えることになります。
削除請求の相手は、投稿者が特定できているのであれば、投稿者にします。
サイト管理者に対して削除請求をすることもありますが、素直には応じてくれないことも多いです。
弁護士が根拠を示して要求し、それでも拒否されたら裁判に訴えることになります。
発信者情報開示請求
誹謗中傷記事の投稿者を特定するためには、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を使います。
通称、プロバイダ責任制限法といいます。
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとされています。
通常は、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続で進めていきます。
投稿者を特定するためには、まずはサイト管理者に対するIPアドレス等の開示を請求します。
次に、接続プロバイダに対して投稿者の住所氏名の開示請求をします。
この開示請求ですが、必ず成功するとは限りません。
接続プロバイダのログ保存期間は3~6か月程度であり、ログが残っていないという結果となることもあります。
接続プロバイダに対して開示請求がなされたら、プロバイダは連絡先を把握している発信者・投稿者に対して開示してよいかを意見照会します。
損害賠償請求
誹謗中傷をした投稿者が特定できたら、損害賠償請求を検討します。
まずは任意で請求し、合意とならなかったら裁判に訴えることになります。
和解となったら、二度と誹謗中書の記事を書きこまない事も含めて約束させることになります。
発信者情報開示請求で裁判手続きを利用していた場合は、その費用も請求できる場合もあります。
刑事事件化
権利侵害が名誉毀損罪や侮辱罪や業務妨害罪等の犯罪が成立するのであれば、刑事告訴をすることになります。
単に被害を警察に訴えただけでは、警察は積極的に動いてくれないこともあります。
ある程度情報を集めてから警察に説明した方が、スムーズに動いてくれることもあります。
ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はインターネットトラブルの解決を通じて、皆様の利益と名誉を守り、安全な社会生活を実現させます。
インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士で組織する専門チームが、インターネットネットトラブルの事案に応じた解決を分析して対応していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部があり、全国のネットワークを生かした迅速な対応が可能です。
迅速な対応が必要となりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
インターネット上の記事を削除したいーインターネットの情報に関する削除請求について解説
違法に動画をアップロードされたらーFC2動画に違法に動画をアップロードした投稿者に損害賠償

動画投稿サイトは数多くありますが、中には違法に動画がアップロードされることもあります。
ここでは、FC2動画にアップロードされた違法アップロード動画の投稿者に対し,損害賠償請求を行う方法について解説していきます。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
A社は動画撮影を行い,動画を販売する会社です。A社がFC2動画に違法アップロードされた動画が無いか調査していたところ,A社の販売する動画が違法にアップロードされているのが発見されました。
そのため,Aさんは,違法にアップロードした犯人を突き止め,損害賠償請求を考えています。
このような場合に,どのような手段でアップロードした人物を特定することができるのか,特定したとして,損害賠償請求を行うことができるのか解説します。
大きな流れとしては,アップロードした人物が誰だか分からないため,そのままでは,損害賠償請求を行うことはできません。
そのため,まず①発信者情報開示請求を行い,②著作権侵害を理由として損害賠償請求を行うという方法で,損害賠償請求を行っていきます。
発信者情報開示請求
まず,コンテンツプロバイダに対して,IPアドレスの開示請求を民事保全手続きの形で行って,次にアクセスプロバイダに対して,IPアドレスとタイムスタンプの開示請求を行います。
アップロードした犯人を特定する方法として,発信者情報開示請求を行うことが考えられます。
FC2の場合,アメリカのネバダ州に本社がある関係から,基本的には,アメリカのネバダ州法のディスカバリ制度を使う必要があります。
そのため,このディスカバリを利用して,アクセスプロバイダのIPアドレスを開示してから,日本国内のアクセスプロバイダに発信者情報開示請求を行い,違法に動画をアップロードした犯人を特定することになります。
このように,裁判を行って,発信者情報の開示請求が認められた場合に,ようやく,名誉毀損の投稿を行った人物の名前と,住所を特定することができます。
損害賠償請求
このように,発信者情報を特定した場合,損害賠償請求に進んでいきます。
損害賠償請求の段階に入ったら,どのような動画の投稿がされたのか,これによってどんな損害を被ったのかということについて審理し,金銭による損害の回復を行う段階に入っていきます。
特に,今回の事例の場合,著作権侵害が問題になっていることから,元の動画のどの部分が違法にアップロードされているのか,著作権は誰にあるのか,損害額はいくらなのか,損害額が算定できないとしても,利用許諾を出すとすればいくらで利用許諾をしていたのかを立証することになります。
今回の事例の場合
今回の事例の場合,まず,FC2 Incにディスカバリによる,IPアドレスとタイムスタンプの開示を求め,次に,NTTなどに対して,発信者情報開示請求を行います。
そこで,ようやく発信者がXと特定され,その人に対して,Aさんが著作権侵害を理由とする損害賠償請求を行って行き,金銭による損害の回復を行うということになります。
注意点
注意点としては,ログの保存期間の関係から,アクセスプロバイダに対して開示請求を行ったとしても開示が認められない可能性もあることや,発信者がXさんと特定されても,書き込みをしたのはXさんの家でインターネットを使ったYさんがアップロードしたと言われてしまい,損害賠償請求が認められないというケースもあります。
もし,インターネットのトラブルにあったため,書き込んだ人を何とかしたいということであれば,弁護士に依頼して,このような形で損害賠償請求を行っていくことになります。
違法に動画をアップロードされてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
動画を削除したいー虚偽情報や誹謗中傷を内容とする動画の削除について解説
ネットトラブルと裁判の証拠ーネットトラブルが起こった場合の証拠の取り方について解説

ネットの投稿というものは,日々刻々と変化していくため,トラブルの元となった投稿が消去されていたり,編集されていたりします。
また,知財高裁平成22年6月29日判決によれば,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な証拠であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」として,問題となる記載だけではなく,URLなど特定するための情報を必要としています。
そのため,トラブルの元となった証拠について何らかの形で証拠化する必要があるため,解説していきます。
サイトの情報を証拠化する方法としては,①スクリーンショットを撮る,②クロームの機能を使って,PDF化する,③紙に印刷する,④パソコンの画面を写真や動画に撮る⑤ウェブ魚拓サイトを利用するという方法が考えられます。
①スクリーンショットを撮る方法
この方法によれば,簡単にパソコンやスマートフォンの画面の問題となる投稿や,そのURLを画像に残すことができます。
しかし,URLが長い場合,パソコンや,スマートフォンの画面内に収まりきっておらず,URLが判別できないと判断される場合があります。
なお,URLが長すぎて画面に収まりきっていない場合,URLをワードファイルなどにコピーして貼り付けておき,一緒に証拠にすることが考えられます。
パソコンで,スクリーンショットを撮る場合,「alt」+「prt sc」をすることで,撮影することができます。
②PDF化する方法
google cromeの機能を使うと,サイトをPDF化することができます。
クロームの右上の縦になった「・・・」をクリックし,「印刷する」を選択し,「送信先」のところを「PDFに保存」に変更することで,PDFファイル化することができます。
なお,この場合のURLの残し方ですが,「詳細設定」にある「ヘッダーとフッター」にチェックを入れることでPDFファイルのデータにURLを残すことができます。
③紙で印刷する方法
google cromeの「印刷する」で紙媒体として出力することも出来ます。
ただし,URLが途中で切れてしまう可能性があるため,その場合には有力な証拠にならない可能性もあります。
④パソコンの画面を写真や動画に撮る方法
パソコンの画面を写真や動画に撮る方法についても,証拠を残す手段として有効です。
ただし,写真に残した場合,URLが全部入り切れない場合があります。
そのため,動画で残すということも考えられます。
⑤魚拓サイトを利用する方法
いわゆる魚拓という当時のサイトの状況についてそのままデータを残してくれるサービスを行っているサイトが存在しています。そのため,そのサイトを利用して証拠化を行うということも有効な手段です。
魚拓を残す方法として,「ウェブ魚拓」というサイトが利用されています。
以上が,ネットトラブルの際の問題となった投稿の証拠化の方法です。
これらを使って,証拠化しておくと,弁護士との法律相談の際にスムーズに話が進みますし,裁判所に提出する有力な証拠として利用することができます。
ネットトラブルにお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
SNSでの投稿の削除についてーXに書き込まれた内容を削除請求できるか
インターネット上での名誉毀損に対する損害賠償請求

インターネット上で名誉毀損となる内容の投稿をされた場合、広範に拡散して大きな被害を受けるおそれがあります。このような場合、投稿をした者を特定して損害賠償を請求することが重要となります。
ここでは、5chに名誉毀損となる内容を書き込まれた場合に,書き込んだ人に対して損害賠償請求できるか解説します。
【事例】
事実を基にしたフィクションです。
AさんはB県C市においてAクリニックを開業している医者です。
ある日,5chの掲示板に「C市のAクリニックの院長が詐欺」というタイトルのスレッドが立ちあげられ,「この前,A院長が『最新の医療機器を導入する必要がある』と言って,C市に補助金を申請していたんです。しかし,今日『医療機器の件どうなりました?』と聞いたら,『買わない買わない,その話は補助金のための嘘だから』と言っていたんです。私としても,こういわれてしまい,どうしたらいいか分からず,ここに書いてみました。」と書き込まれている投稿を発見しました。
Aさんとしては,最新の補助金の申請をして,医療機器を買ったのは本当のことであるにもかかわらず,このような書き込みがされていたため,このような投稿をした人が誰なのかを明らかにして,損害賠償請求をしたいと考えました。
この場合に,発信者情報の開示を行い,書き込んだ人に対して損害賠償請求を出来るか検討していきます。
大きな流れ
このようなインターネットでの名誉毀損が行われた場合,書き込んだ人が誰だか分からないため,そのままでは書き込んだ人に対して損害賠償請求をすることができません。
そのため,まず,①発信者情報開示請求を行って,②名誉毀損を理由とする損害賠償請求を行うことになります。
発信者情報開示請求
まず,コンテンツプロバイダにIPアドレスの開示請求を民事保全請求の形で行い,次にアクセスプロバイダに対してIPアドレスの開示を裁判で行う手続で進んでいきます。
5chである場合,コンテンツプロバイダになるのは,Loki Technology,Incです。
そのため,まず,コンテンツプロバイダに対して,名誉毀損の対象となる投稿をURLやスクリーンショットから特定して,投稿の際に使われたIPアドレスと,ポート番号,送信された日時を開示するように求めます。
すると,コンテンツプロバイダからのIPアドレスの情報開示と,タイムスタンプについての連絡があります。
このように,コンテンツプロバイダからの情報開示があったことから,アクセスプロバイダに対して,発信者情報消去禁止仮処分を請求することになります。
発信者情報消去禁止仮処分が認められた場合,発信者が投稿した際に経由したアクセスプロバイダに対して,発信者情報開示請求の裁判を提起することになります。このアクセスプロバイダというのは,掲示板に投稿する際に使われた通信会社のことを指します。そのため,たとえば,NTTがアクセスプロバイダになります。
このように,裁判を行って,発信者情報の開示請求が認められた場合に,ようやく,名誉毀損の投稿を行った人物の名前と,住所を特定することができます。
損害賠償請求
このように,発信者情報を特定した場合,損害賠償請求に進んでいきます。
損害賠償請求の段階に入ったら,どのような書き込みがされたのか,これによってどんな損害を被ったのかということについて審理し,金銭による損害の回復を行う段階に入っていきます。
今回の事例の場合
今回の事例の場合,まず,Loki Technology,Incに発信者情報の開示を求め,次に,NTTなどに対して,発信者情報開示請求を行います。
そこで,ようやく発信者がXと特定され,その人に対して,Aさんが名誉毀損を理由とする損害賠償請求を行って行き,金銭による損害の回復を行うということになります。
注意点
注意点としては,ログの保存期間の関係から,アクセスプロバイダに対して開示請求を行ったとしても開示が認められない可能性もあることや,発信者がXさんと特定されても,書き込みをしたのはXさんの家でインターネットを使ったYさんが書き込んだと言われてしまい,損害賠償請求が認められないというケースもあります。
もし,インターネットのトラブルにあったため,書き込んだ人を何とかしたいということであれば,弁護士に依頼して,このような形で損害賠償請求を行っていくことになります。
インターネットのトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。