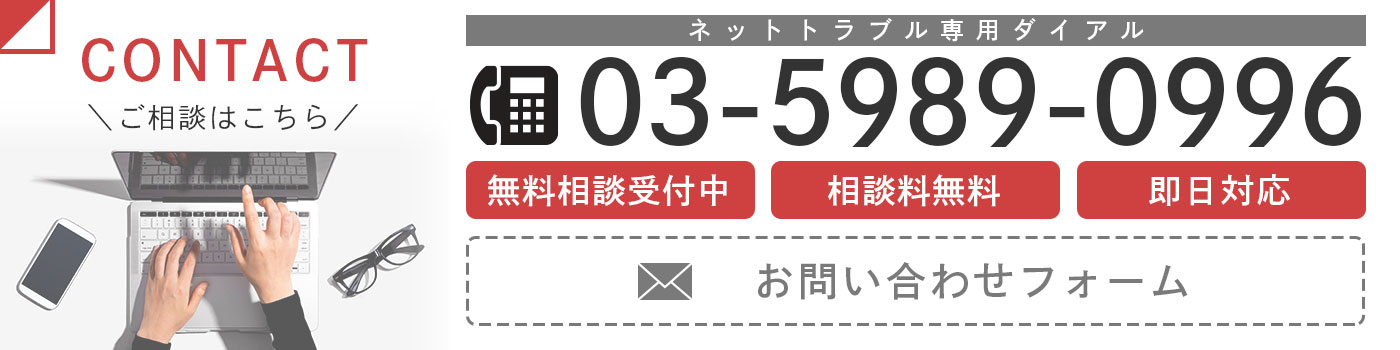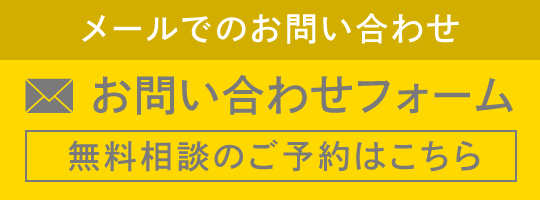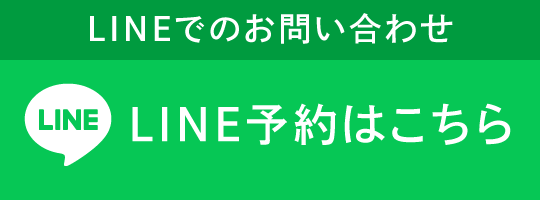少年法とはどんな法律か
少年法1条によれば、この法律の目的について、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定されています。
このことから、少年法というのは保護処分という特別の措置を少年に対して取るということだけでなく、少年に対する刑事事件について定めるということもしています。
この「少年」というのは、20歳に満たない者を指します。なお、令和3年に成人年齢の改正があったことから、18歳以上、20歳未満の者については「特定少年」として扱われます。
少年法の手続に乗るとどのような処分が予定されるのか
家庭裁判所の判断の種類には、①不処分、②児童福祉機関送致決定、③検察官送致決定(逆送決定)、④保護観察、⑤児童自立支援施設・児童養護施設への送致、⑥少年院送致の6種類があります。
①の不処分については、少年の非行事実の存在が認められないとか、この少年については、少年法上の処分をしなくてもよいということでする判断です。刑事裁判で言うところの無罪判決に近いものです。
保護観察にするか、少年院送致にするかの基準については、「要保護性」によって判断されます。
この「要保護性」というのは、①非行事実の犯罪的危険性、②保護処分による矯正教育を施すことによって強制することができるか、③他の処分ではなく、保護処分によるべき必要性の三要素によって決まる。
このように決まることから、社会的には(比較的)軽微な犯罪と考えられる万引きであっても、少年院送致ということになることもあります。
少年院に送られると、3年を超えない範囲の収容となり、社会から隔離され、少年院の中で規則正しい生活を送りつつ、健全な心身の成長を図り、犯罪傾向の矯正に取り組むことになります。
少年事件となった場合に弁護士はどのような対応をするのか
少年法上、弁護士は「付添人」として手続に参加することになります。この「付添人」というのは、少年に対する身柄拘束などの不利益処分に対して、少年の意見を聞き、異議を述べる立場であると同時に、少年審判手続きが適切に進むよう家庭裁判所に協力する立場でもあります。
そのため、理念上は、少年になるだけ軽い処分を求める立場であると同時に、少年に対して厳しいことを言わなければならない立場でもあります。
しかし、現実には、なるだけ軽い処分を求める少年の意見を聞き、その少年の意見が、家庭裁判所の判断に反映されるよう求める立場にあるのだと思われます。
少年審判手続に対する被害者参加
少年審判手続については、少年のプライバシーや、少年の更生のため被害者にも非公開とされてきました。
しかし、現在、被害者は、①被害者への審判結果の通知(少年法31条の2第1項)、②被害者による少年事件の記録の閲覧謄写請求(少年法5条の2第1項)、③被害者からの処分についての意見聴取の機会付与(少年法9条の2)、④少年審判の傍聴(少年法22条の4第1項)という四つの手続の関係から、少年審判手続きに参加することができます。
ただし、少年審判手続の傍聴については、少年の矯正を妨げるおそれがあるかによって可否が判断されるため、被害者参加手続きのうち最もハードルが高いと考えられます。
少年法は少年に甘い法律じゃないのかという疑問に対して
「少年法は少年に死刑を与えないような犯罪者に甘い法律だ」とか、「少年法は少年院送致しかせず、犯罪者に甘い判断をしている」という主張をされることがあります。
しかし、少年法がこのように犯罪を行った少年に対して、刑罰を与えるのではなく、再度の非行、犯罪を行わないようにするための処遇を実施していますし、この処遇や少年院での生活が甘いことはありません。
また、元少年Aの書いた『絶歌』にもある通り、再犯を行わないための活動というのも、成人になって酒を飲むなどは許されないほどの非常に厳しいものですし、何十年経っても少年院に行ったという事実は社会的ペナルティにもなります。
ですので、少年法は少年に必ずしも甘い法律ではありません。